発達障害と診断されて、「どうやって働いたらいいんだろう」「今の職場はしんどいけど、どう変えていけばいいかわからない」と感じていませんか?
私自身も、発達障害と診断された後、さまざまな困難を経験してきました。
今回は、すでに診断を受けている方向けに、「自分らしく働ける場所を見つける」ために活用できる公的な支援についてご紹介します。
私自身は、まだ活用したことはありませんが、調べる中で「こんな支援があるんだ」と驚いたものばかりです。
1. 発達障害者支援センター(都道府県・政令市ごとに設置)
▶ どんなところ?
発達障害者本人や家族、関係者への総合的な支援を行う専門機関です。
▶ できること
- 特性の理解や困りごとへの相談
- 福祉・医療・教育・就労など各分野との連携支援
- 必要に応じた機関への紹介
▶ どんな人に向いている?
- 自分の特性を整理したい人
- どこに相談したらいいかわからない人
- 地域の支援機関とつながりたい人
2. 就労移行支援事業所
▶ どんなところ?
一般企業への就職を目指す障害者に、職業訓練や就活支援を行う福祉サービスです(原則2年間利用可)。
▶ できること
- ビジネスマナー、PCスキルなどの訓練
- 自己理解、職業適性の把握
- 企業見学や実習、就職後の定着支援
▶ どんな人に向いている?
- 働いた経験が少ない、またはブランクがある人
- 一般就労に不安がある人
- 自分の特性に合う職場を探したい人
※利用には原則、障害者手帳または医師の診断書が必要です。
3. ハローワーク(専門援助窓口)
▶ どんなところ?
障害のある方専用の窓口が設けられており、専門の職員が就労支援を行っています。
▶ できること
- 障害特性に配慮した求人の紹介
- 就職面接会、職場体験の案内
- 就職後の職場定着支援(ジョブコーチ支援など)
▶ どんな人に向いている?
- 一般就労を希望している人
- 障害に配慮した働き方を希望する人
4. 地域障害者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
▶ どんなところ?
専門スタッフ(職業カウンセラー・臨床心理士など)が、障害者の職業能力開発や就職を支援します。
▶ できること
- 職業評価(職業適性・作業能力など)
- 就職へのステップ設計
- 職場適応への助言・支援
5. 自立支援医療(精神通院医療)
▶ どんな制度?
精神科の通院医療費の自己負担を軽減する制度です(通常3割→原則1割に)。
▶ 使えるとどうなる?
- 長期の治療や通院を継続しやすくなる
- 経済的負担が軽くなることで、生活全体の安定にもつながる
おわりに
発達障害と診断されたあと、「じゃあどうすればいいんだろう?」と感じることは自然なことです。
でも、私たちの周りには想像以上に多くの支援があります。もちろん、すぐに全てを使う必要はありません。
まずは「こういう支援がある」と知ることが、次の一歩につながるはずです。
必要なときに、必要な支援を。それが「自分に合った環境」を見つける第一歩になりますように。
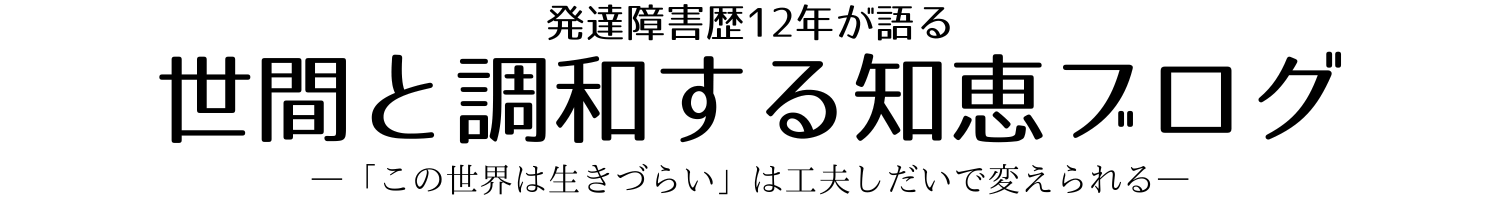


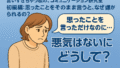
コメント