「助けられる人」って、どんな人でしょうか?
私は、発達障害特有の“ズレ”からくる誤解や衝突を、完全に無くすことはできませんでした。
でもある時から、「この人が困ってるなら助けよう」と思ってもらえるようになった実感があります。
それは、日頃から“ちょっと便利な人”として信頼残高を積みながら、小さな工夫を重ねてきたからです。
この記事では、実際に私がやってきた「職場で助けられる人になるための工夫」を、すぐに使える7つの行動例として紹介します。
1. 手伝うときは「確認」から入る
「この仕事、今からやってもいいですか?」
ただの一言ですが、これを言うか言わないかで、相手の受け取り方は大きく変わります。
勝手にやってしまうと「ありがた迷惑」になることもあるし、「人の仕事を勝手に奪った」と思われてしまうこともあります。
相手に確認を取ることで、感謝されやすく、摩擦が起きにくくなります。
2. 「見て覚える」より「聞いて確認」が確実
私は「見て覚えて」と言われるのが一番苦手です。
自分の解釈で動いてしまうと、ズレてしまうことが多く、結局やり直しになることも。
それなら、はじめから「これはこのやり方で合ってますか?」と確認したほうが確実です。
また、確認した内容をメモして復唱することで、相手に安心感も与えられます。
3. 表情や声のトーンに意識を向ける
発達障害のある人の中には、表情が乏しく見えたり、声のトーンが単調で冷たく聞こえたりする傾向があります。
私もそのひとりです。
無意識のうちに無表情になってしまい、「怖い」「不機嫌そう」と思われていたこともあります。
ほんの少し、口角を上げて話すだけで、印象はだいぶ変わります。
意識して表情と声に気を配るようにすると、人間関係がスムーズになりました。
4. 「ありがとう」「助かりました」は忘れずに
助けてもらったとき、「ありがとう」ときちんと伝える。
それだけで、相手は「この人をまた助けてもいいな」と思ってくれます。
シンプルですが、とても大事なことです。
また、「助かりました」「本当にありがたかったです」と、具体的に何が嬉しかったのかを伝えると、相手の満足感も高くなります。
5. 「自分ルール」ではなく「相手の基準」に合わせる
発達障害のある人は、独自のこだわりやルールを持ちやすい傾向があります。
私も、「こうあるべき」と思い込みがちなところがあります。
でも、職場は自分一人で動いているわけではないので、周囲のやり方や基準に合わせることも大切です。
もちろん、全部を無理に合わせる必要はありません。
「これなら無理なくできる」というラインを見極めて、必要以上に自己犠牲しないことも同じくらい重要です。
6. 困ったときに正直に助けを求める勇気
ミスを隠したり、できないことをできるフリをするのは、長い目で見て逆効果です。
私は以前、「これお願いできますか?」と言われて、よく分からないまま引き受けてしまい、大きなトラブルになったことがありました。
それ以来、「すみません、やったことがないのですが教えてもらえますか?」と正直に言うようにしています。
日頃から誠実に行動していれば、こうしたSOSも受け止めてもらいやすくなります。
7. 小さな気配りを“習慣化”する
たとえば、備品を整える、仕事の準備を手伝うなど、小さな気配りを毎日の中で少しずつ続けていく。
これが習慣になると、特別な努力をしなくても「気が利く人」「信頼できる人」という印象を持ってもらえます。
気配りが当たり前になることで、周囲からの信頼も自然と積み重なっていきます。
まとめ
「助けられる人」になるためには、日々の積み重ねと、素直なコミュニケーションが大切です。
発達障害の特性を持つ私たちにとって、“ズレ”は避けられないものですが、それを責められる前に「この人なら助けたい」と思ってもらえる土台を作ることで、生きやすさは確実に変わっていきます。
次は、あなたの職場で1つでも取り入れてみませんか?
📩 コメント・質問歓迎
記事の内容に関するご感想や、「こんなことが知りたい」というリクエストがあれば、ぜひお気軽にコメントしてくださいね。
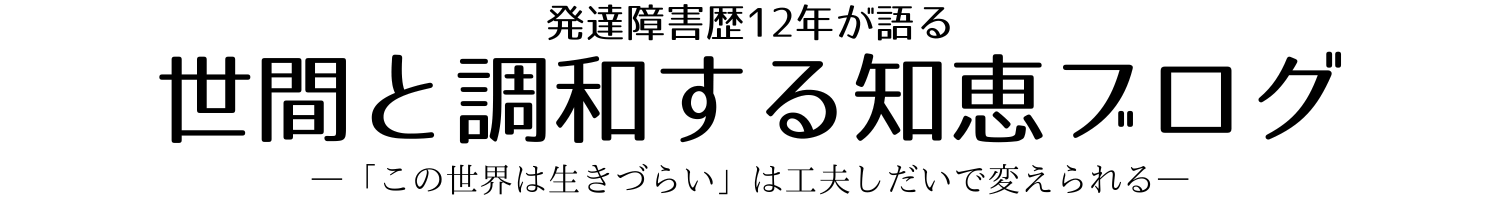
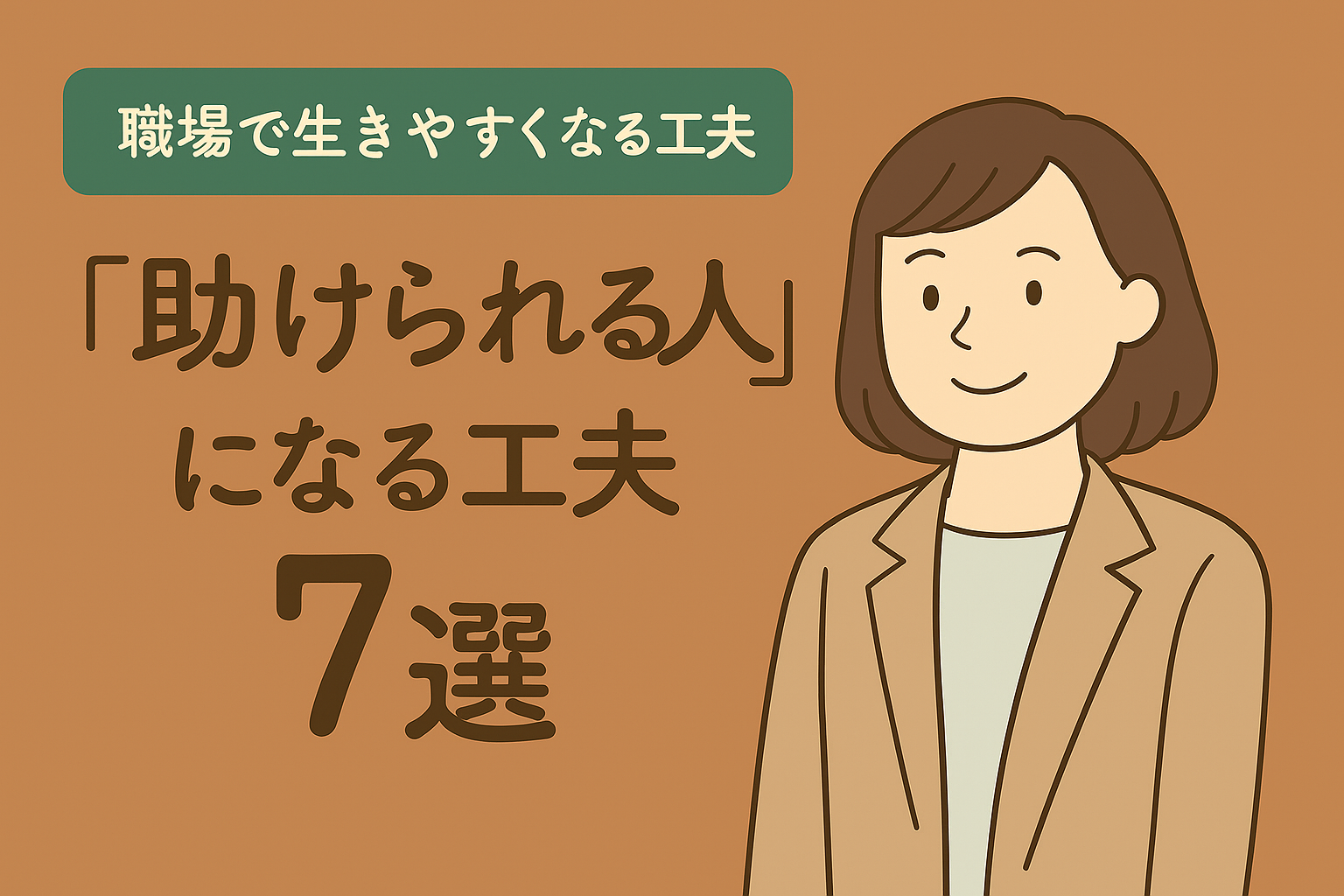
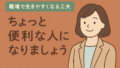
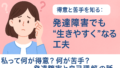
コメント