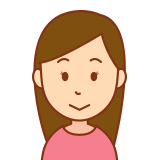
傾聴と共感は分かるけど…
とりあえず傾聴?とりあえずって何よ。
理解できなくても共感?理解してないのに共感なんてできなくない?
こう思ったそこのあなた。あなたは正しいです。仰るとおりでございます。笑
でも、発達障害(特にアスペルガー症候群)のような、デフォルトのコミュニケーション能力が低い人間にとっては、これは有効な方法です。
私自身も毎日この方法を実践していますし、おかげさまでコミュニケーションのストレスがかなり減ったと感じます。
人と関わることが苦手だと感じているなら、豆知識として覚えておいて損はありません。「こんな方法もあるんだな〜」と思いながら読んでもらえたら嬉しいです。
コミュニケーションの基礎基本 傾聴と共感の威力
そもそも「傾聴」と「共感」とは何でしょうか。
傾聴とは、相手の話に耳を傾け、その内容や気持ちを否定も肯定もしないで受け止めることです。話を遮らず、相槌を打ちながら最後まで聞き、相手の気持ちや感情を理解しようとする姿勢が大切です。
共感とは、他者の感情や経験を理解し、それに寄り添う能力です。これは単なる同情とは異なり、相手の立場に立ってその感情や考え方を自分ごととして感じることです。
傾聴と共感の技術を効果的に使えると、相手に「この人は自分のことを分かってくれた」と感じてもらい、無意識に自分の味方であると認定してもらうことができます。信頼関係の構築にとても効果的です。
日常生活において、人間は他人と会話する際、自然に傾聴と共感をして、コミュニケーションをとっているものです。人間関係を円滑にするために、傾聴と共感は必須です。
しかし、コミュニケーション能力が低いアスペルガー症候群などの発達障害は、この技術が元々備わっていません。
普通は成長とともに自然に習得し、できるようになるのですが、発達障害の場合は自分が何もしなければ一生身につきません。
ではどうするか。自分で意識して、努力して、後天的に身に付けるしかありません。
アスペルガー症候群はコミュニケーションが苦手
そもそも、アスペルガー症候群はなぜコミュニケーションが苦手なのでしょうか。
アスペルガー症候群の特性については以下の通りです。
アスペルガー症候群は広い意味での「自閉症」に含まれる一つのタイプで、「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」「パターン化した行動、興味・関心のかたより」があります。自閉症のように、幼児期に言葉の発達の遅れがないため、障害があることが分かりにくいのですが、成長とともに不器用さがはっきりすることが特徴です。
あしたの暮らしをわかりやすく 政府広報オンラインより引用
最近はアスペルガー症候群ではなく、「自閉スペクトラム症(ASD)」という診断名を使用されるようになってきていますが、個人的にアスペルガー症候群という名称が馴染み深いので、このブログではアスペルガー症候群という名称を使用しています。
この「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」は、次のような症状となって現れます。
こころの健康がみえる 第1版 p203 より引用
- 他人の考えや感情を推測しにくい
- 身ぶりや表情を読み取りにくい
- 人間関係を築き、保つのがのが苦手である
これを、もっと噛み砕いて説明していきます。
他人の考えや感情を推測しにくい
他人の考えや感情を推測することが困難で、言外の意味を推測できないです。言われた言葉を、言葉通りの解釈しかすることができません。
所謂、「空気が読めない」「冗談が通じない」はここからきています。
ちなみに、私自身も10代の頃は、空気が読めないと散々言われてきましたが、当時この「空気が読めない」という表現そのものが全く理解できなかったです。
当時繰り広げていた会話がこちら。笑
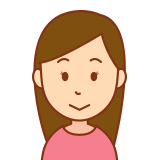
ほんとに空気読めないよね〜www
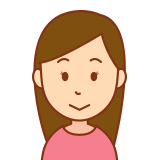
空気は読むものじゃなくて、吸うものでしょ?何言ってるの?
今では笑っちゃいますが、当時は本気で空気は吸うものだ、読むってなんだと言われるたびに思ってました。アスペルガー症候群のみなさんには、気持ちを分かってもらえるのではないかと思います。
また、相手の気持ちを想像することができないので、「この話に興味なさそうだな」「嫌がってそうだから話変えようかな」という考え方ができません。
結果、相手の反応を一切気にせず、自分しか興味のない話を永遠と続けて相手を辟易とさせてしまったりします。会話も一方通行になりがちです。
身ぶりや表情を読み取りにくい
基本的に他人の表情の変化に気づきにくいです。幼少期からアイコンタクトが少なく、親の表情を参照しないことが特徴的です。
そもそも他人の表情をあまり見ようとしないし、見ても何も読み取れません。
普通は表情の変化を観察すると、相手の喜怒哀楽を想像できます。人間は、発言内容と本音は一致していないことも多く、本音と建前を使い分ける生き物です。言葉だけでは本音はわからないからこそ、表情の変化で本音を推測します。
例えば、言葉で「大丈夫」と言っていても、表情が全く大丈夫じゃなさそうだったら、「大丈夫じゃなさそうだから、助けたほうが良いだろう」と普通の人間は考えることができます。
ですが、アスペルガー症候群に「大丈夫」と言ったら、どんなに苦しそうな表情をしていたとしても「大丈夫って言ってるからいいだろう」という思考になります。
これにより、思いやりの心が足りないとか、性格が悪いと思われがちで、本当に損をします。
本人に悪気は全く無いです。性格も悪くないです。「大丈夫じゃないから助けてくれ」って言われたら、言われた通りに助けます。単純に「言葉をその通り受け取っている」「苦しそうな表情がわからない」だけなんです。
人間関係を築き、保つのがのが苦手である
そもそも他人に興味関心を示さず、相手に合わせるということができません。幼少期から、ごっこ遊びをしないで1人で遊ぶのが好きだったり、同年代の仲間に興味を示さないのが特徴的です。
根本的に「他人に興味がない」から、友達を作るだけで一苦労、それを維持するのはもっと大変です。
そもそも人間関係というのは、「この人はどんな人なんだろう」という興味関心を相手に向けて、はじめて成立するものです。
世間一般の大多数の人間は、この興味関心を維持し続けられるからこそ、「最近どうしてるかな」と相手の近況を知りたいという発想に至ります。そこから連絡を取る・食事に誘うなどの行動に移したりしています。
これにより、誘われた相手は「この人は自分のことを心配してくれているんだな、大事に思ってくれているんだな」と感じることができます。
実際に会って、近況を話し合い、悩みや愚痴を聞いてもらい、そこで傾聴・共感をされると「この人は私のことを理解してくれた、味方になってくれた、これからも仲良くしたい」と無意識に考えるものです。
そして、今後も仲良くしたいとお互いが感じている場合は、この繰り返しになります。お互いが相手に対して興味関心を抱いているからこそ、何かしらの行動をするでしょう。定期的にどちらかが「会おうよ」と声を掛け合い、人間関係が維持されるという仕組みです。
アスペルガー症候群の「他人に興味関心を抱かない」という特徴は、人間関係を構築する上で、かなり不利になります。
相手のことを知りたいとも思わないのだから、自分からは当然声をかけません。せっかく相手から声をかけてきてくれても、聞かれたことには答えても、そこから相手について質問しようという発想になりません。興味がないからです。
アスペルガー症候群が世間で生きていくためには、「自分は他人に興味関心がないんだ」という、とても残念な事実をきちんと認識する必要があります。
そのうえで、本心では興味関心を抱いていなくても、ただの情報収集として相手の話を聞くスキルを習得する必要があります。先天的に身についていないので、生きるための技術として、後天的に習得しましょうということです。
コミュニケーションが苦手な理由
ここまで、アスペルガー症候群に特徴的な、「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」になりやすい症状について説明しました。主な症状は以下3つでした。
- 他人の考えや感情を推測しにくい
- 身ぶりや表情を読み取りにくい
- 人間関係を築き、保つのがのが苦手である
アスペルガー症候群は、なぜコミュニケーションが苦手なのでしょうか。簡単にまとめましょう。
- 言外の意味を推測できず、本音と建前を理解する能力がそもそも低い
- 表情の変化を読み取る能力も低いから、より相手の本音を推測することが困難
- 他人への興味関心がないから、人間関係維持のために自発的に行動しない
つまり、相手の本心を読み取る材料が根本的に不足していて、さらに相手そのものにも関心が持てないという、人間関係構築に必要な要素がまるごと不足してる状態なんですよね⋯…
これでコミュニケーションをできるわけがありません。当然の結果です。元々備わっている能力が低いだけです。この事実を正しく認識することが、人間関係構築のための第一歩です。
できないものは「できない」と認めましょう。それができたら、次は「どのように対策するか」というフェーズに移ることができます。
「傾聴と共感」を擬似的に習得
では、アスペルガー症候群が、社会で困らず生活できるレベルのコミュニケーション能力を習得するための対策方法がこちらです。
「とりあえず傾聴 理解できなくても共感」
この「とりあえず」「理解できなくても」という枕詞がポイントです。
世間一般でよく言う「傾聴と共感」とは違います。あれはアスペルガー症候群にとって手の届かないハイレベルな技術です。これから私が紹介するのは、「傾聴と共感」を擬似的に習得する方法です。
そもそも、世間一般でよく言われる傾聴と共感とは、以下のようなものです。
- 相手の話に耳を傾け、その内容や気持ちを否定も肯定もしないで受け止めること
- 話を遮らず、相槌を打ちながら最後まで聞き、相手の気持ちや感情を理解しようとすること
- 他者の感情や経験を理解し、それに寄り添う能力
- 単なる同情とは異なり、相手の立場に立ってその感情や考え方を自分ごととして感じること
一般的な傾聴と共感は、「相手の話を聞いて、気持ちや感情を理解する」という点が共通していますが、これをできるようになろうと思ったら、レベルが高すぎて間違いなく挫折します。
アスペルガー症候群は、本音と建前の違いや表情の変化が分からず、そもそも他人に興味関心がありません。本当の意味で相手の考えを理解しようとする「傾聴と共感」をすることは、ほぼ不可能です。
ですが、相手の気持ちや感情を理解できなかったとしても、「まるで傾聴と共感をしているかのように振る舞う」ことは、練習すれば可能です。むしろこちらの方が圧倒的にハードルが低くて、望みがあります。
では、具体的にどうすればよいでしょうか?説明していきます。
とりあえず傾聴
まず、一般的な「傾聴」をおさらいしましょう。
- 相手の話に耳を傾け、その内容や気持ちを否定も肯定もしないで受け止めること
- 話を遮らず、相槌を打ちながら最後まで聞き、相手の気持ちや感情を理解しようとすること
そして、私が目指す「とりあえず傾聴」はこちらです。
- 遮らずに話を聞く
- 適切な相槌をうつ
- 要点を整理して解釈一致しているか確認する
ご覧の通り、似ているけど違います。「受け止める」「気持ちや感情を理解する」のようなふんわりとしていて、結局どうすればいいのか分からない部分を変更しています。
だって「受け止める」「理解する」って言われても、どういう基準をクリアしたらできたことになるのか、全然明確じゃないですよね。
特にアスペルガー症候群は、曖昧な表現が苦手です。なにができたらクリアしたことになるのか、目標は明確に設定する方が良いと思います。
では、一つずつ具体的に解説していきましょう。
遮らずに話を聞く
相手の言いたいことが一通り終わるまでは、話を遮らないでひたすら聞くだけです。簡単そうに見えますが、これをきちんとできる人は案外少ないです。
世間一般でも、ついつい相手の話を遮って、話題を奪って、自分の話したいことを話してしまう人は多いです。だからこそ、相手の話を遮らずに、最後まで聞くことができる人間の存在は貴重です。
ここで注意するのは、自分と考えが違う時、「でもさー」と途中で反論してはいけないということです。相手の主張が終わるまで、自分の意見は胸の中に留めておき、相手の主張内容をきちんと把握します。
自分の意見を押し殺すわけではありません。「自分とは違う意見」として把握するだけです。違う意見だからこそ、最後まで聞かないと、正確に内容を把握することができません。
相手の考えを正確に把握して、自分の解釈と一致しているか確認した上で、「貴方の考えは〇〇だよね。私は✕✕という考えをもってるんだ。貴方は私の考えについてどう思う?」と建設的な意見交換に繋げます。
相手と意見が違っても、このような話し合いができれば、対立することも険悪な雰囲気になることもありません。むしろ信頼関係の構築に繋がります。
とりあえず、最後まで遮らずに聞きましょう。これが第一歩です。
適切な相槌をうつ
遮らずに話を聞くときに、ただ聞いているだけで何の反応も返さなければ、相手は「この人、本当に話聞いてる?」と不審に感じます。
そこで大切なのが、適切な相槌をうつことです。これにより「私は貴方の話を聞いてますよ」と相手にアピールすることができます。
適切な相槌ってなんでしょう?テクニックは色々ありますが、最初は簡単なものから始めましょう。
- 「はい」「ええ」「うん」を徹底的に極める
- 相手の話に合わせてうなずく
- 相槌をうつ時に相手の目を見る
- 相手の話す内容と自分の表情・相槌のトーンをなるべく一致させる
1.「はい」「ええ」「うん」を徹底的に極める
目上の人には「はい」、真面目な場面では「ええ」、フラットな関係なら「うん」が使いやすいです。
相手が話すテンポに合わせて、合間に「はい」「ええ」「うん」という相槌を挟みます。これは多様しすぎは逆効果になるので、たまに挟むくらいがちょうど良いと思います。
また、「はいはい」「は〜い」のような使い方は、相手からすると蔑ろにされている印象になる場合があるので、避けたほうがよいです。「はい」は1回!延ばさない!が原則です。
まずはこの3つを使えるようになりましょう。勿論、相槌のフレーズには他にも沢山種類があります。
基本ができるようになったら、「効果的な相槌」で検索すればテクニックは山程出てきますから、自分で勉強して、使える種類をだんだん増やせばよいです。
2.相手の話に合わせてうなずく
最初は難しく考えずに、相手のはなすペースに合わせて、「はい」「ええ」「うん」と相槌をうつタイミングで、一緒にうなずきましょう。
慣れてきたら、場面や話す内容に合わせて「深くゆっくり」「繰り返す」「早く繰り返す」など、バリエーションを持たせると効果的です。
3.相槌をうつ時に相手の目を見る
話を聞くときは、基本的に相手の目を見て話しましょう。
ただ、ずっと目を見つめているのは怖いので、話すときは相手の眉間あたりをぼんやり見ておいて、相槌をうつタイミングでたまにしっかりと目線を合わせるくらいで良いと思います。
「目は口ほどにものをいう」という言葉があるように、しっかり目を見て相槌をうつことで、相手は「しっかり話をきいてくれている」と感じやすくなります。
4.相手の話す内容と自分の表情・相槌のトーンをなるべく一致させる
楽しい話なら明るい表情、悲しい話なら神妙な表情というように、話の内容と自分の表情をなるべく一致させます。相槌のトーンも変化させられるとなお良いです。
少しハードルが高いですが、最初は一致を目指すのではなく、「話の内容と、相槌がズレている」ことがないように気にする程度でも十分です。
悲しい話をしているのに、明るく相槌をうたれると「話きいてる?絶対わかってないでしょ」と思われるので、相槌が逆効果になります。まずはズレないようにだけ頑張りましょう。
要点を整理して解釈一致しているか確認する
適切な相槌をうちつつ、話を遮らずに最後まで聞いたら、はじめて自分から話します。
ここで大切なのは、相手の話した内容の要点を整理して伝えて「今の話を聞いて、貴方の主張は〇〇だと私は思ったんだけど、これで解釈合ってる?」と確認します。
「貴方はこう思ってるんだよね?」と確認することで、それがちゃんと一致していれば、相手は「私の考えを理解してもらえた」と感じます。
一致していなければ、おそらく「そうじゃなくて、✕✕ってこと」と相手から訂正がはいりますから、最終的には相手の考えを正確に把握することが可能です。
これで、実際には相手の考えを理解できなくても、相手からは「話を聞いてもらえた」「理解してもらえた」と感じてもらえます。
「理解はしていない」けれど、一つの意見として「把握はできている」という状況です。これが、私が目指す「とりあえず傾聴」の全貌になります。
これを読んでいる、コミュニケーションが苦手なあなた。どうでしょうか。これならちょっと頑張ればできそうじゃないですか?
理解できなくても共感
次は、共感について説明していきます。
世間一般でよく言われる共感とは、以下のようなものです。
- 他者の感情や経験を理解し、それに寄り添う能力
- 単なる同情とは異なり、相手の立場に立ってその感情や考え方を自分ごととして感じること
そして、私が目指す「理解できなくても共感」はこちらです。
- 「他人の考えは完全には理解できない」と心得る
- 一部分同意 「分かる〜〜〜」
- 全く同意できない場合 「なるほど〜」「勉強になります」
はい。見ての通り全くの別物になっております。
なぜかというと、世間一般の共感は、そもそもアスペルガー症候群にはハードル高すぎて無理だからです。「理解する」「寄り添う」「自分ごととして感じる」とか、どう考えてもできません。難しすぎます。
なので、最初から「他人の考えは完全には理解できない」という前提で、擬似的な共感を演出することを目指します。相手からしたら「理解してもらえた」という印象になるので、結果オーライです。
では、具体的な方法をご紹介していきます。
「他人の考えは完全には理解できない」と心得る
そもそも、他人の考えを完全に理解するなんて無理なんですよ。だって違う人間なんですから。自分の考えを本当の意味で理解できるのは自分だけです。
でも、「相手の考えを分かろうと努力する」ことは可能です。前述した「とりあえず傾聴」を実践できていれば、完全に理解はできなくても、相手の考えを把握することが可能になります。
これができている時点で、相手からは「話を聞いてもらえた」「理解してもらえた」という印象をもたれやすいです。
まずは、他人の考えは完全には理解できないと心得た上で、「とりあえず傾聴」ができるように練習しましょう。
一部分同意 「分かる〜〜〜」
一般的な共感には「相手に寄り添う」「自分ごととして感じる」という要素が含まれます。これを具体的に表現できる、魔法のフレーズがあります。
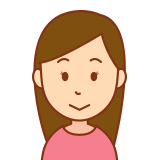
分かる〜〜〜
はい。これです。目上の人に対しては「分かります」「気持ち分かります」「心中お察しいたします」のように言い換えましょう。表現は色々あります。
「私は貴方の意見に同意してますよ」「貴方の味方ですよ」をアピールできる、とても便利な言葉です。
ただし、無闇矢鱈に、いつでもどこでも誰にでも使ってたら、「絶対嘘だろ」と不審に思われます。
特にアスペルガー症候群は、嘘を付いたり、本心と違うことを言うのが苦手なので、全く同意できない内容に対しては、使用しないほうが無難です。
相手の主張を把握して、ほぼ同意できた、もしくは一部分同意できた場合に使用しましょう。
例えば「同僚の1人が全然仕事をしてくれなくてイライラする」という愚痴を、友達から言われたとします。自分にも同じような経験があって、理解できる感情だなと思ったら、同意すればよいです。
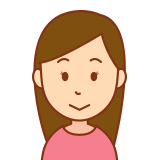
分かる〜〜〜!自分ばっかりに負担がくるから嫌になっちゃうよね!そういう人って、どこにでもいるんだね、大変だよね〜〜〜
みたいな感じです。
少しも同意してないのに「分かる〜〜〜」って言うと、相手にそれが伝わります。「この人、いつもテキトーなことしか言わないよな」と信用を失います。
完全に逆効果ですので、絶対にやめましょう。
全く同意できない場合 「なるほど〜」「勉強になります」
相手の話を聞いていて、こんなことありませんか?
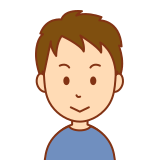
いやいやいや…全く理解できないんだが…この人何言ってるんだろう?
アスペルガー症候群は特に、世間一般と感覚がズレていることが多いです。私自身も、他人と会話していて、正直全く理解できず、同意できないことも多いです。
そんなときは「こんな風に考える人間もいるんだな」「自分とは違う価値観を勉強させてもらおう」という気持ちで、より一層気合を入れて相手の話を聞きましょう。
そして、相手の主張を一通り把握し「とりあえず傾聴」を実践します。そして、最後に一言添えましょう。
目上の人なら
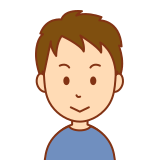
そんな考え方もあるんですね!自分では思いつかなかったので、勉強になります。
フラットな関係なら
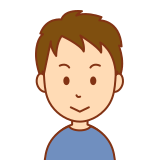
なるほど〜確かにそういう考え方もできるね!
こんな感じです。全く意味が分からないと思っても、とりあえずこう返しておけば、反感をもたれることはありません。
大切なのは、相手の主張を否定しないことです。これは、自分の考えを押し殺すこととは全く違います。
相手の主張はきちんと聞いて、内容を正しく把握したうえで、「私は〇〇だと思う」と自分の意見もしっかりと伝えればよいだけです。
反対意見を伝えるときは「Iメッセージ」
相手の意見と自分の意見が全く異なる場合、反対意見を伝えるときの、誰でもすぐに使えるテクニックがありますので、紹介しておきます。
「Iメッセージ」と呼ばれる技法です。
簡単に言うと、「私は〇〇がいいと思う」「私はあなたに〇〇して欲しい」というように、主語を「私」にして相手に自分の希望や意見を伝えるという手法です。
人間って会話するとき、主語を「私」にしてないことが多いんです。特に、相手に愚痴や文句を言いたい時はそれが顕著です。
よくやりがちなのは「普通は〇〇して当然でしょ」「あの人は〇〇してくれたのに」のように、比較対象として世間の常識や第三者を利用してしまうパターンです。
この言い方をすると、相手が不愉快に感じやすく、喧嘩や対立に発展しがちです。
常識や第三者の価値観を持ち出して否定されると、「そんなの知らねぇよ」「じゃあその人に頼めばいいだろ」という感じで、反発したくなるのが人間なんですよね。
これは本当に良くないので、心当たりのある方は、今すぐやめましょう。主語を「普通」「あの人」にして、コミュニケーションがうまくいくことはほぼありません。
素直に謙虚にシンプルに、「私は〇〇がいいと思う」「私はあなたに〇〇して欲しい」と伝えると、なぜかスッと受け入れやすくなり、やってあげたくなるのが人間の不思議なところです。
簡単で、かなり効果的なテクニックですので、ぜひ試してみてください。
まとめ
- アスペルガー症候群はコミュニケーションが苦手
- 言外の意味を推測できず、本音と建前を理解する能力がそもそも低い
- 表情の変化を読み取る能力も低いから、より相手の本音を推測することが困難
- 他人への興味関心がないから、人間関係維持のために自発的に行動しない
- 「とりあえず傾聴 理解できなくても共感」で傾聴と共感を擬似的に習得
- 遮らずに話を聞く
- 適切な相槌をうつ
- 要点を整理して解釈一致しているか確認する
- 「他人の考えは完全には理解できない」と心得る
- 一部分同意 「分かる〜〜〜」
- 全く同意できない場合 「なるほど〜」「勉強になります」
- 反対意見を伝えるときは「Iメッセージ」
アスペルガー症候群には特性として「コミュニケーションの障害」「対人関係・社会性の障害」があります。他人とのコミュニケーションが苦手なことが多いです。
他人の考えや感情を推測することが困難で、言外の意味を推測できないです。言われた言葉を、言葉通りの解釈しかすることができません。所謂、「空気が読めない」「冗談が通じない」はここからきています。
また、身ぶりや表情の変化を読み取る能力も低いです。表情から相手の喜怒哀楽を想像することができず、発言内容と本音が一致していない場合にそれを見抜けません。本音と建前を使い分けることが困難です。
さらに他人に興味関心を示さず、相手に合わせるということができません。人間関係維持のために、自発的に行動したりすることが少ないです。
つまり、相手の本心を読み取る材料が根本的に不足していて、さらに相手そのものにも関心が持てないという、人間関係構築に必要な要素がまるごと不足してる状態です。
そんなアスペルガー症候群が、社会で困らず生活できるレベルのコミュニケーション能力を習得するための対策方法として「とりあえず傾聴 理解できなくても共感」を紹介しました。
これは傾聴と共感を擬似的に習得する方法です。相手の気持ちや感情を理解できなかったとしても、「まるで傾聴と共感をしているかのように振る舞う」ことは、練習すれば可能です。
「とりあえず傾聴」は、相手の話を遮らずに最後まで聞き、合間に適切な相槌をうち、要点を整理して解釈一致しているか確認することが大切です。
「理解できなくても共感」は、最初から「他人の考えは完全には理解できない」という前提で、擬似的な共感を演出することを目指します。
相手の意見に一部分同意できる場合は「分かる〜〜〜」「気持ち分かります」という言葉で、相手の意見に同意していることを伝えます。ただし、無闇矢鱈に使用すると不審に思われるので注意しましょう。
相手の意見を全く理解できない場合は、「こんな風に考える人間もいるんだな」「自分とは違う価値観を勉強させてもらおう」という気持ちで、より一層気合を入れて相手の話を聞きましょう。
そして最後に「自分では思いつかなかったので、勉強になります」「なるほど〜そういう考え方もできるね」と一言添えておきましょう。これで反感を買うことはありません。
反対意見を伝える時には「Iメッセージ」が効果的です。「私は〇〇がいいと思う」「私はあなたに〇〇して欲しい」というように、主語を「私」にして相手に自分の希望や意見を伝えるという手法です。
「普通は〇〇して当然でしょ」「あの人は〇〇してくれたのに」のように、比較対象として世間の常識や第三者を利用してしまうと、相手が不愉快に感じやすく、喧嘩や対立に発展しがちです。
素直に謙虚にシンプルに、主語を「私」にして伝えるだけで、なぜかスッと受け入れやすくなり、やってあげたくなります。とても簡単で効果的なので、オススメです。
私は10年以上かけて、この技を編み出しました。傾聴と共感はアスペルガー症候群にとって難易度が高いですが、できるようになると便利です。
本来の傾聴と共感は無理でも、自分でもできそうなように改良して実践していくと、コミュニケーションのストレスが段違いに減りました。
社会で生活し、人間関係を良好に維持するためには、必要なスキルだと思います。できそうなものがあったら、ぜひ試してみてください。
読者の方へ
このブログは、発達障害と診断されたけどどうしていいか分からず困っている方や、診断はされていないけど、とにかく毎日生きづらくて仕方がないという方に届いたら良いなと思って書いております。
見てくださった誰かが、少しでも肩の力を抜ける、息がしやすい生き方ができる、人と関わることを毛嫌いせずにもうちょっと頑張ってみようかな、と思ってもらうきっかけ作りができたら本当に嬉しいです。
私が10年間で身につけた方法や個人的な見解を書いておりますので、医学的に証明されていたり根拠があるものではありません。
専門家からみたら間違っている点もあるかと思いますが、あくまで個人の意見ですのでご了承下さい。
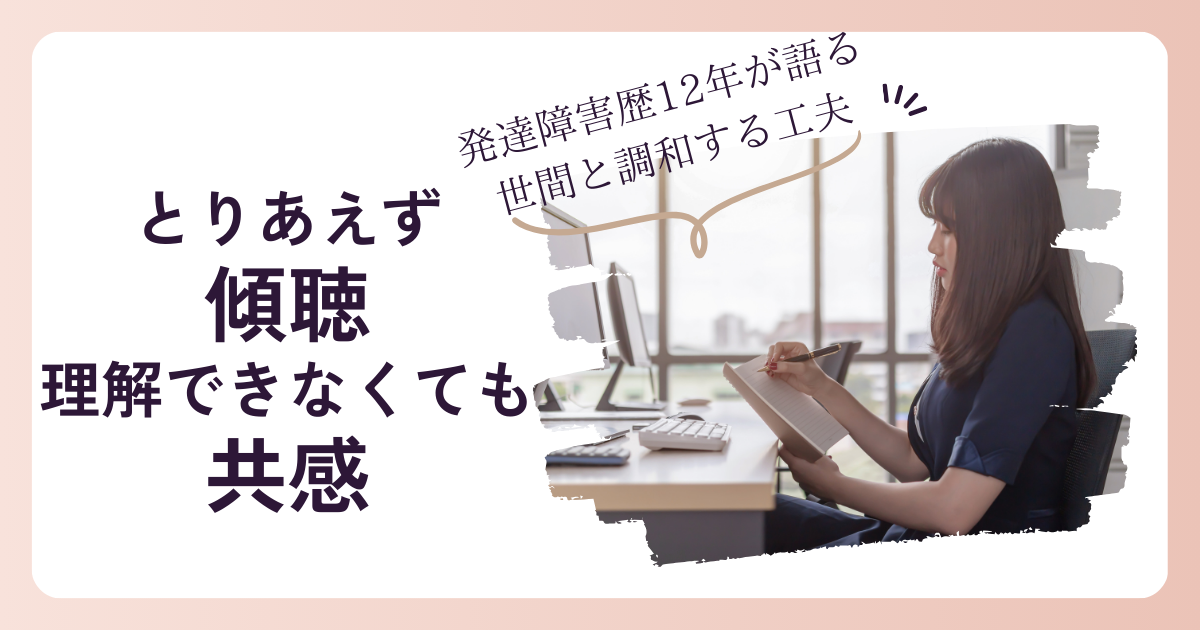

コメント