ワークキャンプ中に何度も設けられていたのが、1対1で向き合って“本音で話す”という時間でした。
特にテーマはなく、「今、話したいこと」「聞いてほしいこと」をただゆっくり、順番に語り合うだけ。
最初は緊張していたけれど、次第に少しずつ、自分の気持ちを言葉にできるようになっていきました。
少しずつ言語化できるようになってきた「心の内」
私はこれまで、「自分のことを話す」のが得意ではありませんでした。
誰かに心の内を見せるのが怖くて、黙っていたほうが楽だったから。
でも、ワークキャンプで向き合った人たちは、ただ静かに、まっすぐに私の話を聞いてくれました。
遮らず、急かさず、評価もせず——そのままの言葉を、ちゃんと受け止めてくれる人がいる。
その安心感のなかで、私は少しずつ、自分の本当の気持ちを話すことができるようになっていきました。
「どうして私は学校に行けなくなったんだろう?」
色んな人と対話していたとき、よく質問されたことがありました。
「どうして学校に行けなくなったの?」「なんかきっかけってあったの?」
それは、ずっと心の中にあった問いでしたが、明確な答えは出ていませんでした。
対話を重ねるうちに、その答えのようなものが少しずつ見えてきました。
「勉強ができる=自分の価値」だった
私は、小さい頃から「勉強ができる子」として扱われてきました。
人間関係がうまくいかなくても、成績さえ良ければ認められる——そんな風に思っていたし、実際それが唯一の“自分の価値”でした。
でも、高校に入ってから周囲のレベルが一気に上がり、「上には上がいる」と感じた瞬間、自分の中で何かが崩れました。
勉強でも勝てない、人付き合いもうまくいかない、努力しても追いつけない。
そう感じたとき、自分には何も残らないような気がして、足が止まってしまったのかもしれません。
発達障害や精神疾患を「免罪符」にしようとしていた私
また、もうひとつ気づいたことがありました。
私は、自分が「発達障害だから仕方ない」「精神疾患があるから生きづらいんだ」と、どこかで割り切ろうとしていたことです。
人とうまく関われないことも、気分の波があることも、「発達障害だから」「精神疾患だから」と自分に言い聞かせる。
そのことで、少し安心しようとしていたのだと思います。
でも、対話を通して思ったのは、「発達障害・精神疾患であること」は理由になっても、すべての免罪符にはならないということでした。
私は本当は、人ともっと関わりたいし、伝えたいことだってたくさんありました。
そしてそれは、「自分が変わる勇気と行動力があれば叶えられる望みだ」と、気づくきっかけになりました。
本当は、「人とつながりたい」と思っていた
実は私は、ずっと「人付き合いが苦手」「人と関わるのが怖い」と思って生きてきました。
だけどその一方で、漫画やアニメの「友情」や「仲間」に心から惹かれてきたことも、事実でした。
その理由を、ワークキャンプの代表の方との対話の中で、教えてもらったのです。
「それって、本当は“信頼できる関係”を求めてる証拠なんじゃない?」
自分では気づいていなかったけれど、私はずっと「信頼できる人とつながりたい」と思っていた。
その願いが、「作品への興味」という形で強く反映されていたのだと、そこで初めて理解しました。
言葉にすることで、自分の深層に触れていく
この日々の中で、私は「話すたびに、自分を知っていく」感覚を何度も味わいました。
頭の中ではごちゃごちゃしていたことも、口に出して誰かに聞いてもらうことで、はっきりと輪郭を持つようになる。
そして、それが「自己理解」へとつながっていったのです。
次回予告
第4回:「今日は無理かも」からの一歩
——メンタルが沈み、起きられなかった朝。
「今日は休みたい」と伝えた私に、スタッフがかけてくれた言葉は、今の私を支える“行動の原点”になっています。
📩 コメント・質問歓迎
記事の内容に関するご感想や、「こんなことが知りたい」というリクエストがあれば、ぜひお気軽にコメントしてくださいね。
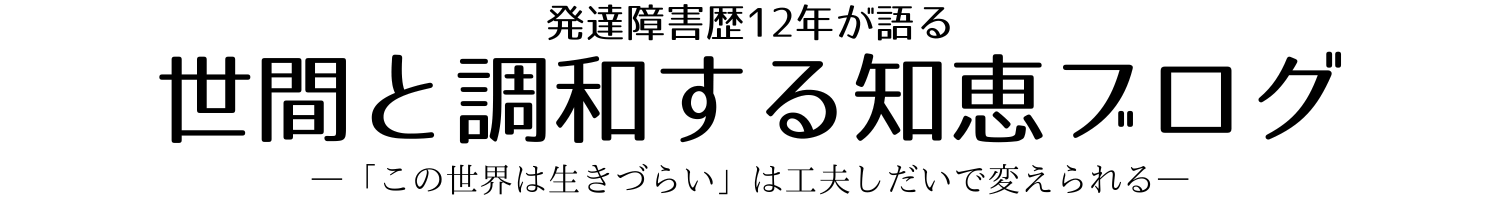
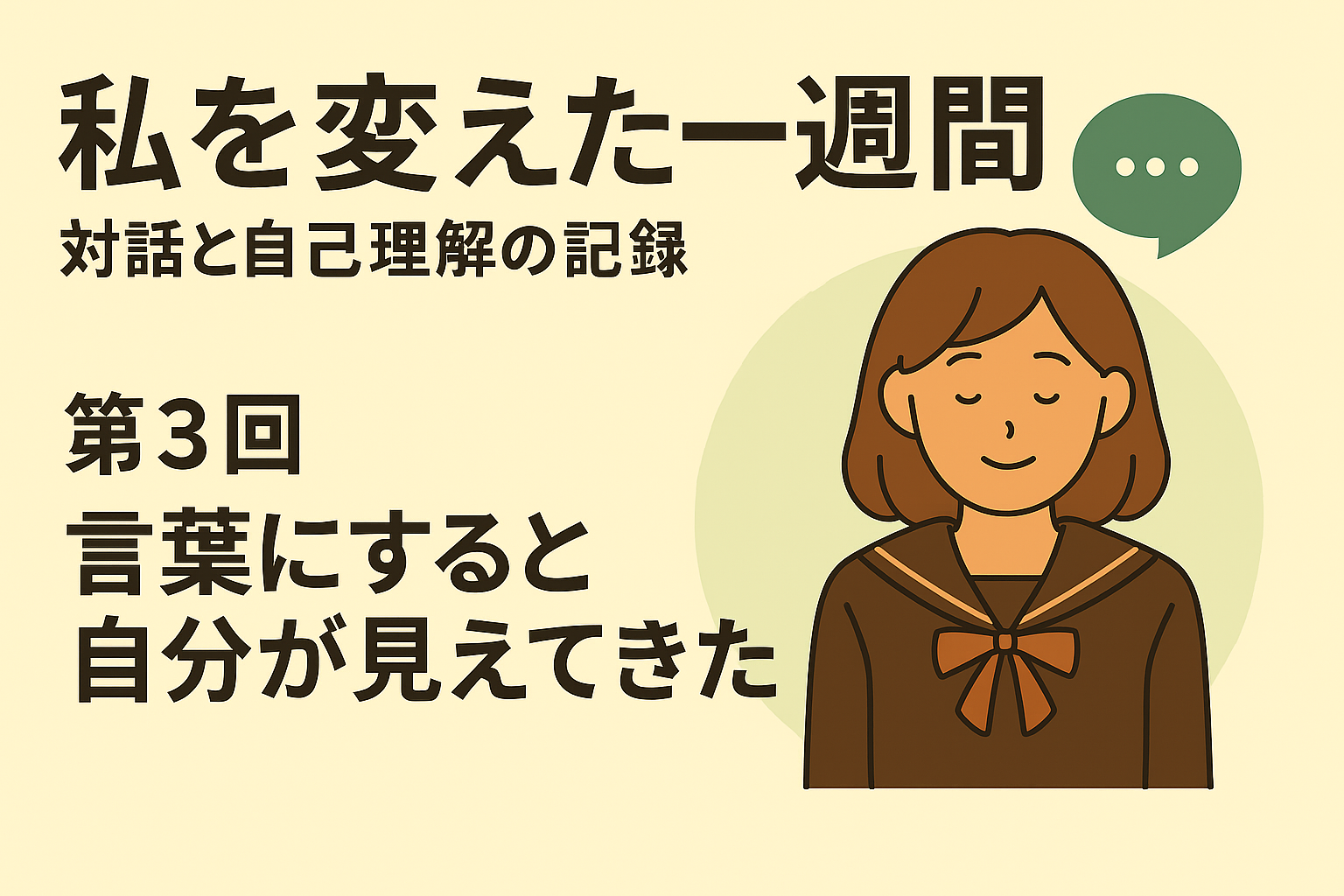
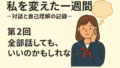
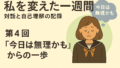
コメント