“向いてない仕事”を続けることの、しんどさ。
私はそれを、身をもって体験しました。
新卒で配属されたのは希望していた手術室——でも、現実は想像以上に厳しいものでした。
大学時代の「努力でなんとかなった」成功体験
大学生のときの私は、「努力すれば、向いてないことでも何とかなる」と信じていました。
実際、大学時代にやっていた派遣アルバイト(ホテルやブライダル関係)では、自分には向いていないと感じながらも、場数を踏むことで最低限の仕事はこなせるようになりました。
「特別に怒られない」「問題を起こさずに終えられる」というだけで、自信に繋がったのです。
その成功体験が、「苦手でも頑張れば乗り越えられる」という思い込みにつながっていました。
だからこそ、新卒で看護師として就職する時も、「看護師は向いてなさそうだけど、きっと努力すればどうにかなる」と思っていたんです。
手術室を希望した理由
私が新卒で配属されたのは、希望していた手術室でした。
希望していた理由は主に4つ。
- 病棟と比較すると、患者さんとのコミュニケーションが少ないこと
- 手術そのものに興味があったこと
- 翌日に入る手術の勉強が前日にできること
- 手術で使う器具や手術の流れがある程度マニュアル化されていて、事前に把握できること
病院実習(実習していた病院に就職)や就職活動のインターンで得た情報だけをもとに、「これなら自分でもやっていけるかもしれない」と思い、配属希望を出しました。
現実は想像以上だった
最初の数ヶ月は、予習して手術に臨む余裕がありました。
けれど、ある程度慣れてくると、状況は一変します。
「次、この手術に入ってきて」と突然言われ、急いで休憩中に勉強し直す。そんな日々が当たり前になりました。
しかも、手術には「正解」がありません。
同じ手術でも執刀医によってやり方や好みが全然違います。
それに、手術は「ナマモノ」です。
出血が多くなったり、予期しない状況が起こるのは日常茶飯事です。
そんな中で求められるのは、「臨機応変な対応」「瞬時の判断」「効率の良い行動」。
まさに、私が最も苦手とする要素ばかりでした。
病棟に異動しても、やっぱり苦しかった
手術室では限界を感じ、体調も崩して休職。
その後、病棟に異動しましたが、ここでも厳しい現実が待っていました。
病棟でも、効率よく情報を整理し、優先順位をつけて動くことが求められます。
また、突発的な患者対応、ナースコール、他職種との連携など、常にマルチタスク状態。
どんなに頑張っても、仕事が終わらず、周囲との能力差がどんどん明確になる日々。
「このまま続けるのは、無理かもしれない」と、やっと思えるようになりました。
私は「努力すればなんとかなる」という言葉を信じすぎて、無理を続けてしまっていました。
でも今は、「無理なことは、無理でいい」と言えるようになりました。
次回予告
ただ、その“無理”に気づいたときには、すでに心も体も限界を迎えていたのです——。
第3回:適応できない仕事で、自分が壊れていった
精神的に限界を迎え、「適応障害」と診断された私。
休職、異動、そして看護師を手放すまでの過程を、次回お話しします。
📩 コメント・質問歓迎
記事の内容に関するご感想や、「こんなことが知りたい」というリクエストがあれば、ぜひお気軽にコメントしてくださいね。
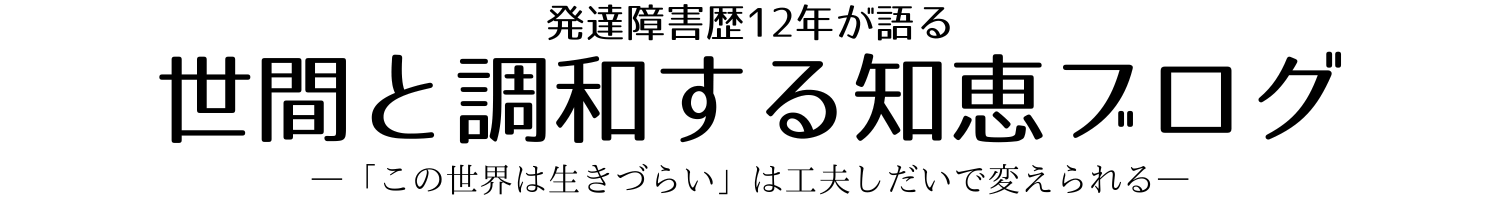
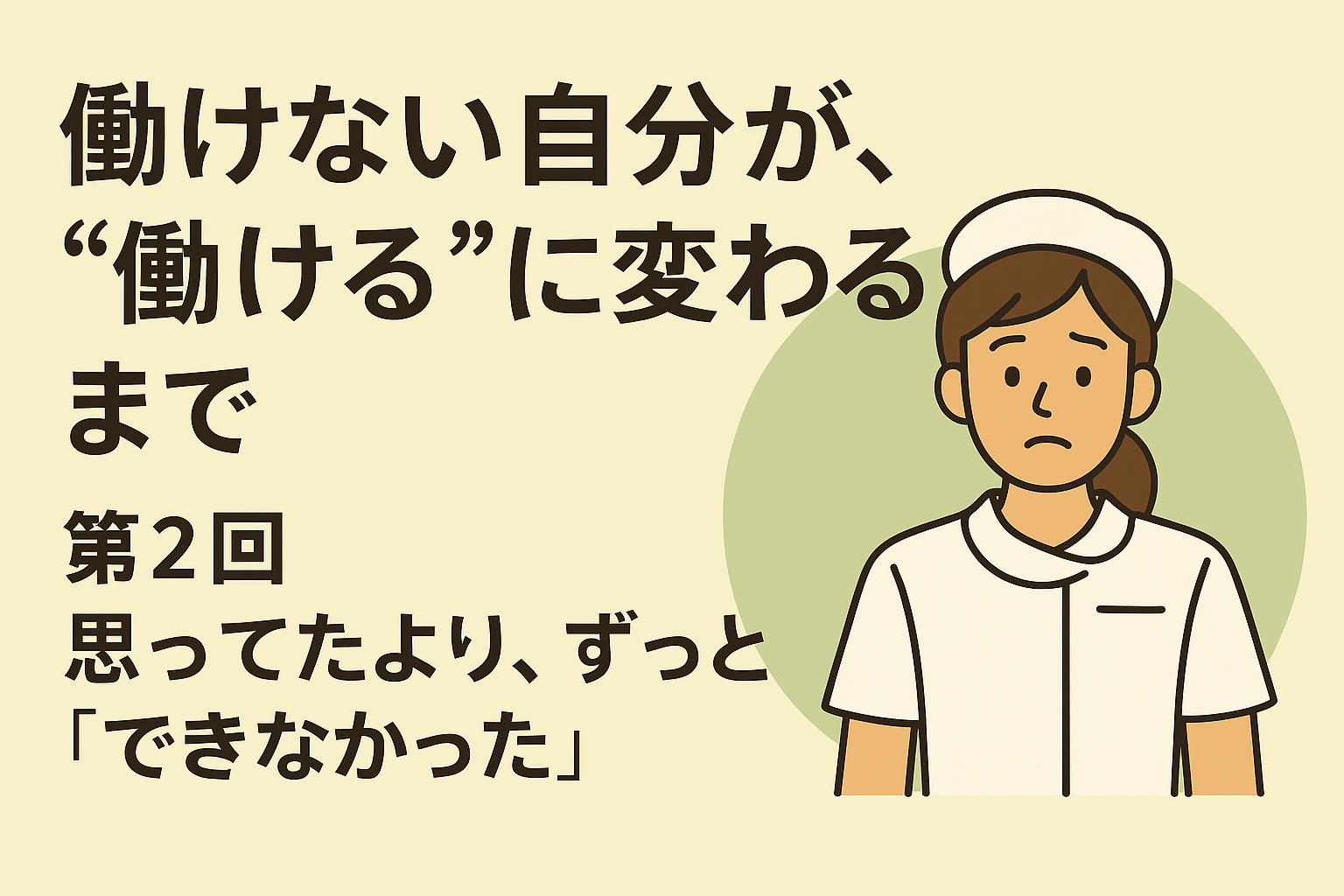
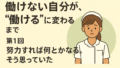
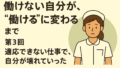
コメント