前回は、「毎日がしんどい」と感じる原因を、言葉にして整理する方法を紹介しました。
今回はもう一歩進んで、自分の「得意」と「苦手」を把握していくステップをお伝えします。
発達障害のある私たちにとって、自己理解は“生きやすさ”の土台です。
「どんな環境に適応できるか」を見つけるためには、まず「自分を知ること」から始まります。
自分を知ることが、なぜ重要?
環境を選ぶには、比較対象が必要です。
つまり、「自分はどういうときに力を発揮しやすく、どんなときにうまくいかないか」という自分自身の使用説明書のようなものを作っておく必要があります。
私自身、この作業を怠っていたことで、「向いていない場所」に飛び込み、必要以上に自分を責めることになってしまいました。
ステップ1:自分で書き出す(得意・苦手の棚卸し)
まずは、紙でもスマホでも良いので、思いつくまま書き出してみることから始めましょう。
▼ 得意なことを見つけるヒント
- 「こんなの簡単」と思っていたら周囲に驚かれたこと
- 気づいたら何時間も没頭していたこと
- やっていて苦じゃない・楽しいと感じる作業
- 感謝されたり、褒められた経験が多いこと
- 疲れていてもできること/つい手を出してしまうこと
▼ 苦手なことを見つけるヒント
- 頑張っているのに毎回つまずくこと
- 人に指摘されることが多い・注意される場面
- 作業に取りかかるまでに時間がかかること
- 無理してやると極端に疲れてしまうこと
- 「なぜか居心地が悪い」「落ち着かない」と感じる場面
ステップ2:信頼できる他者に聞いてみる
ある程度自分で整理できたら、次は周囲の目線を取り入れましょう。
家族や友人、信頼できる上司や同僚など、本音を言ってくれる相手に
「私の得意なこと・苦手なことって何だと思う?」と聞いてみましょう。
他者からのフィードバックは、思い込みを修正するきっかけになります。
ステップ3:(必要に応じて)専門家の力を借りる
「自分の特性がどうしてもわからない」
「対人関係がうまくいかず悩んでいる」
そんなときは、精神科や心理士などの専門家に相談するのも選択肢のひとつです。
私は、高校生の時、精神科受診をして、WAIS(知能検査)や心理検査を受けました。
自分の発達特性を知ることができたのは、とても大きな財産になったと思っています。
発達障害かどうかだけでなく、どんな支援が有効かという視点で、自己理解を深めることができるのが、専門家を頼るメリットです。
私が整理して見えたこと
書き出しと他者の意見、診断を総合して、私の「得意・苦手」はこうでした。
✅ 得意
- 一人で集中して黙々と作業する
- 手順やマニュアルに従うこと
- 情報を文章化・整理する作業
- 相手の話をじっくり聞くこと
🚫 苦手
- 急な変更やイレギュラー対応
- 同時に複数のことをこなす
- 抽象的な指示を読み取る
- 雑談やその場の空気に合わせること
おわりに:得意も苦手も、あなたの「道しるべ」
「自分は何が得意で、何が苦手なのか」
それをちゃんと知っておくだけで、向いていない環境を避ける力が身につきます。
苦手を責めるのではなく、「それが求められない場所」に身を置くことが、私たちの“生きやすさ”に繋がります。
次回は、得意・苦手を踏まえて、どんな環境が合うのかを考える方法を紹介していきます。
次回予告
第4回:自分に合った環境を選ぶという視点
「苦手を頑張って克服する」より、「得意が活かせる・苦手が許される」環境で生きるという選択肢。
自分に合った環境の見つけ方について、具体的に考えていきます。
📩 コメント・質問歓迎
記事の内容に関するご感想や、「こんなことが知りたい」というリクエストがあれば、ぜひお気軽にコメントしてくださいね。
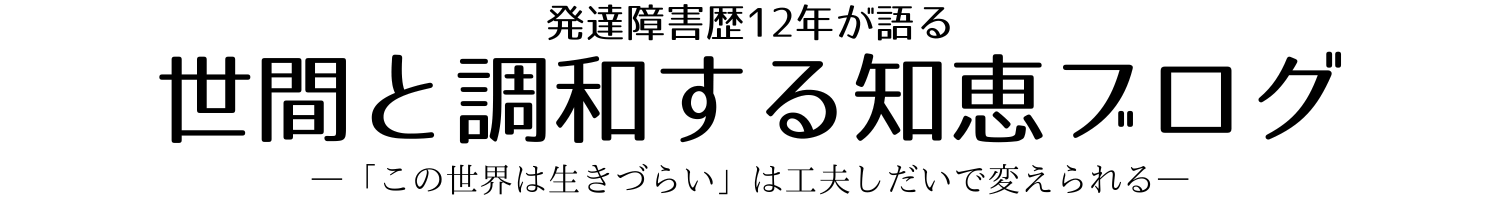
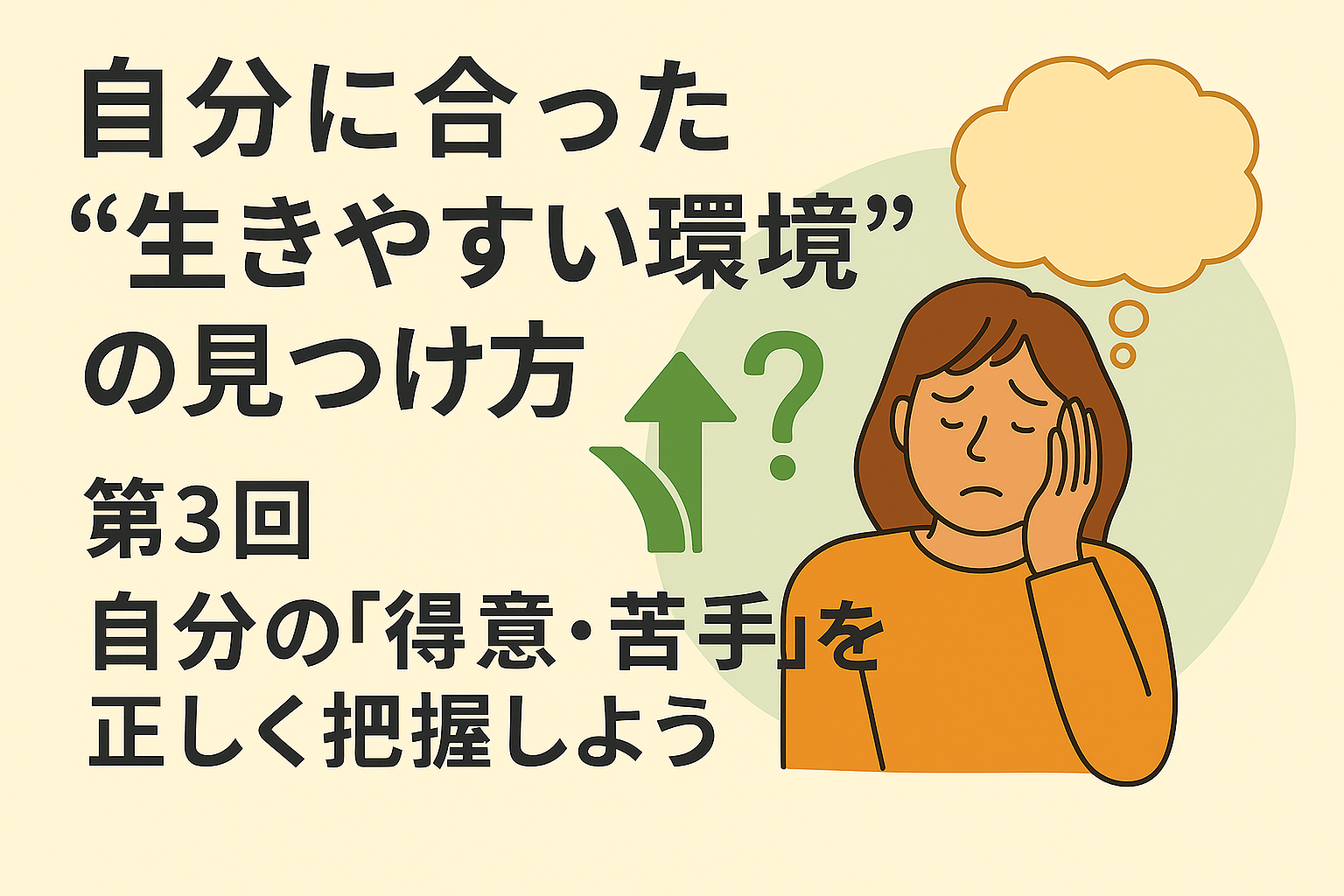
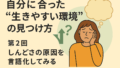
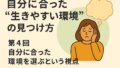
コメント