「傾聴と共感って、よく聞くけど実際どういう意味?」
発達障害のある私にとって、このテーマは避けて通れないものでした。
看護学部で学び、看護師として働く中で「人の話を聞く力」「気持ちに寄り添う姿勢」は必須スキル。でも私は明らかに苦手でした。
それでも、どうにか“それっぽく振る舞う方法”を試行錯誤しながら、今では人間関係のストレスがかなり軽くなっています。
今回はそんな「傾聴と共感の基本」について、発達障害の視点からお話しします。
「傾聴」とは?
まず「傾聴」という言葉、聞いたことはあっても、意味をしっかり説明できる人は少ないかもしれません。
簡単に言うと、
相手の話に耳を傾け、否定せず、受け止めようとする姿勢
のことです。
- 話を途中で遮らない
- 相手が話し終わるまで待つ
- あいづちを打ちながら、真剣に聞く
このような「聞く姿勢」が、傾聴には含まれます。
相手の話を最後まで聞いてもらえると、「ちゃんと話せた」「受け止めてもらえた」と感じやすくなります。それが信頼関係の第一歩になります。
「共感」とは?
「共感」もよく使われる言葉ですが、これもややあいまいです。
よくある誤解は、「同じ気持ちになること」だと思ってしまうこと。でも、実際にはそれよりもっと広い意味があります。
相手の気持ちや立場を想像し、寄り添おうとすること
が、共感です。
完全に理解できなくても、「この人はこう感じているのかも」と想像し、そこに気持ちを寄せること。つまり、
- 「つらかったんだね」
- 「そう感じたの、分かるよ」
といった“寄り添いの言葉”や表情・声のトーンなども、共感を伝える手段になります。
傾聴・共感がなぜ重要なのか?
なぜ、こんなに「傾聴と共感」が大切だと言われるのでしょう?
答えはシンプルです。
人は、自分の気持ちを理解しようとしてくれる人に安心感を持つから
特に、つらいとき・困っているとき・誰かに話を聞いてほしいとき。
話を「ちゃんと聞いてくれる人」や「自分の感情を否定しない人」がそばにいるだけで、人はホッとします。
つまり、傾聴と共感は、人間関係を築くための“土台”なんですね。
でも、発達障害には難しい…
ここで問題が一つ。
傾聴と共感は、とても重要なのに、発達障害とくにアスペルガー傾向のある人には苦手なことが多いです。私もそうでした。
- 相手の感情が読みにくい
- 言外の意味が分かりにくい
- 人の話を聞いても、つい“自分ごと”にすり替えてしまう
これらは、努力だけではどうにもならない「脳の特性」です。
だからこそ「擬似的な習得」が役に立つ
でも私は、「本当の共感は難しくても、それっぽく振る舞うことはできる」と気づきました。
- とりあえず話をさえぎらず聞く
- 話が終わったら要約して返す
- 気持ちを否定せず「そうなんだね」と声をかける
こうした“型”を身につければ、「この人は話をちゃんと聞いてくれる」と相手に思ってもらえるようになります。
これが、私の考える「擬似的な傾聴と共感」です。
このシリーズで伝えたいこと
このシリーズでは、発達障害の特性をふまえたうえで、傾聴・共感・伝え方をどう工夫すれば人と関わりやすくなるのかを、できるだけわかりやすく解説していきます。
苦手でも、やり方次第でどうにかなる。
そう思えるヒントが、ひとつでも見つかればうれしいです。
📩 コメント・質問歓迎
記事の内容に関するご感想や、「こんなことが知りたい」というリクエストがあれば、ぜひお気軽にコメントしてくださいね。
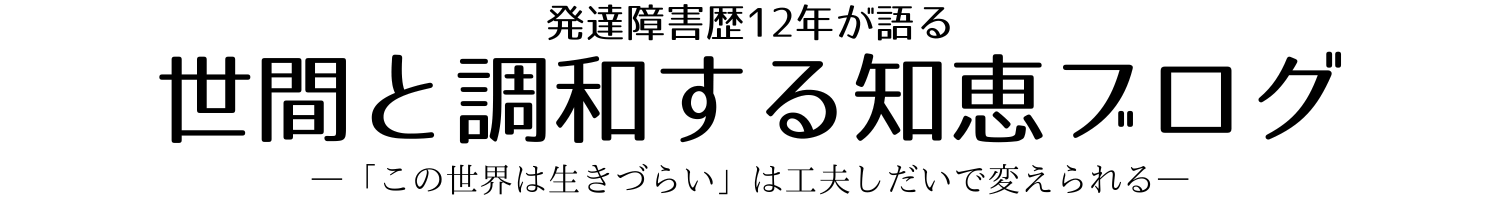

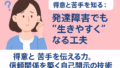
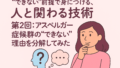
コメント