「同じことを言っているのに、あの人は好かれて、私は嫌われる」
そんな場面に、心当たりはありませんか?
私はずっと、「言い方や表情に気をつければ、伝わり方は変わるはず」と思っていました。
でも実際は、それだけでは足りなかったんです。
人は、“言われた内容”ではなく、“誰に言われたか”で反応する
私が人との関わりの中で学んだのは、
「信頼関係があるかどうか」で、同じ言葉でも受け取り方がまるで変わるということです。
やわらかく伝えても、関係性ができていない相手には「自己中心的」「口出しされた」と感じさせてしまうことがあります。
逆に、信頼関係ができていれば、少し強めの言い方でも「あの人が言うなら、たぶん私のためを思ってくれてるんだな」と受け止めてもらえることもあります。
つまり、伝え方よりも前に、「誰が言うか」が評価を大きく左右する。
そしてその「誰か」になるために必要なのが、日頃の信頼関係の積み重ねです。
信頼があれば、ちょっとのミスも許される
思い返してみてください。
- きつい言い方をされても「まぁ、あの人だから仕方ないか」と思えたこと
- 素直に受け止められたアドバイスには、普段から信頼できる人の姿があったこと
人は、相手との関係の中で、発言の“意味”を判断しているんです。
だからこそ、
- 表情
- トーン
- 言葉の選び方
に気をつけることも大切ですが、それはあくまで「信頼関係がないときの補助技術」。
信頼を築けていれば、それらに頼らなくても伝わる場面が増えていきます。
信頼関係づくりは、伝え方の“上位互換”なのです。
言っている内容より、「誰が言うか」で変わる
SNSや職場などで、「同じこと言ってるのに、あの人はなぜか許されてる」という場面を見かけたこと、ありませんか?
私はそういう場面を何度も見てきて、ようやく気づきました。
信頼関係があると、多少キツいことでも受け入れられるんだと。
逆に、信頼がないまま本音を伝えようとすると、「自己中心的」「上から目線」と受け取られることもある。
内容や表現だけにこだわるよりも、その人が“普段どう接しているか”が、発言の印象を左右していると強く感じます。
それ以降私は、伝える内容そのものよりも、まずは関係性を育てておくことを優先するようになりました。
信頼関係は、戦略的に築いていける
もちろん、信頼関係は一朝一夕ではつくれません。
でも、ASDの私たちにできることもたくさんあります。
- 小さな感謝を伝える
- 話を最後まで聞く
- 名前をきちんと呼ぶ
- 相手の話した内容を覚えておく
- 普段から周りを助ける行動を心がける
そんな細やかな積み重ねが、「この人は私を大切にしてくれている」という安心感を育てます。
そして、信頼関係があれば、“ちょっと伝えにくいこと”も届きやすくなる。
だから私は、発言する前に、まず「関係性を育てる努力」を忘れないようにしています。
コミュ力の高い人は、感覚でやってる。私たちは戦略でいこう
世の中には、こうしたことを感覚でやってのけるすごい人たちがいます。
でも、ASDの私はそうはいきません。
だったら、戦略的に、再現可能な工夫を積み重ねていくだけ。
無理にうまくやろうとしなくても、「この人にだけは心を開きたい」と思える相手との信頼を少しずつ育てていけば、きっと“伝わる”瞬間は増えていきます。
おわりに
人との関係は、正しさや言い方だけでは築けません。
でも、ちょっとした工夫や意識の積み重ねで、関係性は確実に変わっていきます。
完璧じゃなくていい。
でも、「関係を育てていこう」という姿勢があるだけで、伝わり方は変わる。
今日から、できることを少しずつ取り入れてみませんか?
私もまだ途中です。でも、あきらめずに続けていきたいと思っています。
オススメ記事
【シリーズ】職場で生きやすくなる工夫(全3回)
「ちょっと便利な人」になって、周囲と気持ちよく働く方法について紹介しています。
- 第1回:「職場でうまくやれない」のは発達障害のせい?失敗続きの私が気づいたこと
- 第2回:「ちょっと便利な人」になる方法|アスペルガーでも信頼される職場の立ち回り方
- 第3回:発達障害の私が実践している「職場で助けられる人」になる小さな工夫7選
【シリーズ】言いすぎちゃう私の、コミュニケーション研究室(全3回)
「言いすぎてしまう」「本心を素直に言っただけなのに引かれてしまう」——そんな私の実体験をもとに、発達特性ゆえの“コミュニケーションのすれ違い”と向き合ってきた道のりをお届けします。
📩 コメント・質問歓迎
記事の内容に関するご感想や、「こんなことが知りたい」というリクエストがあれば、ぜひお気軽にコメントしてくださいね。
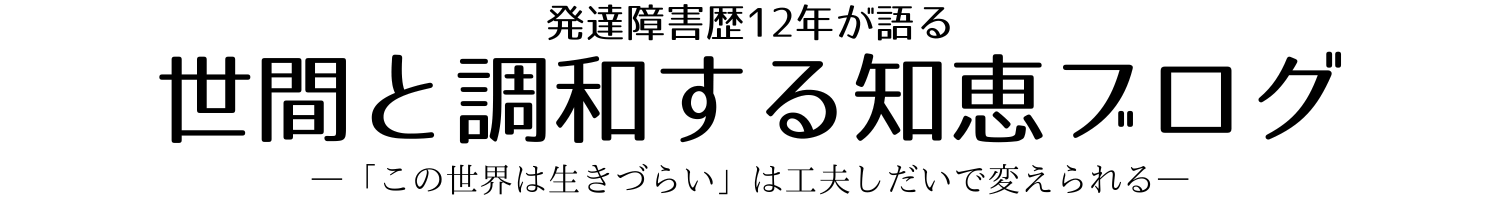
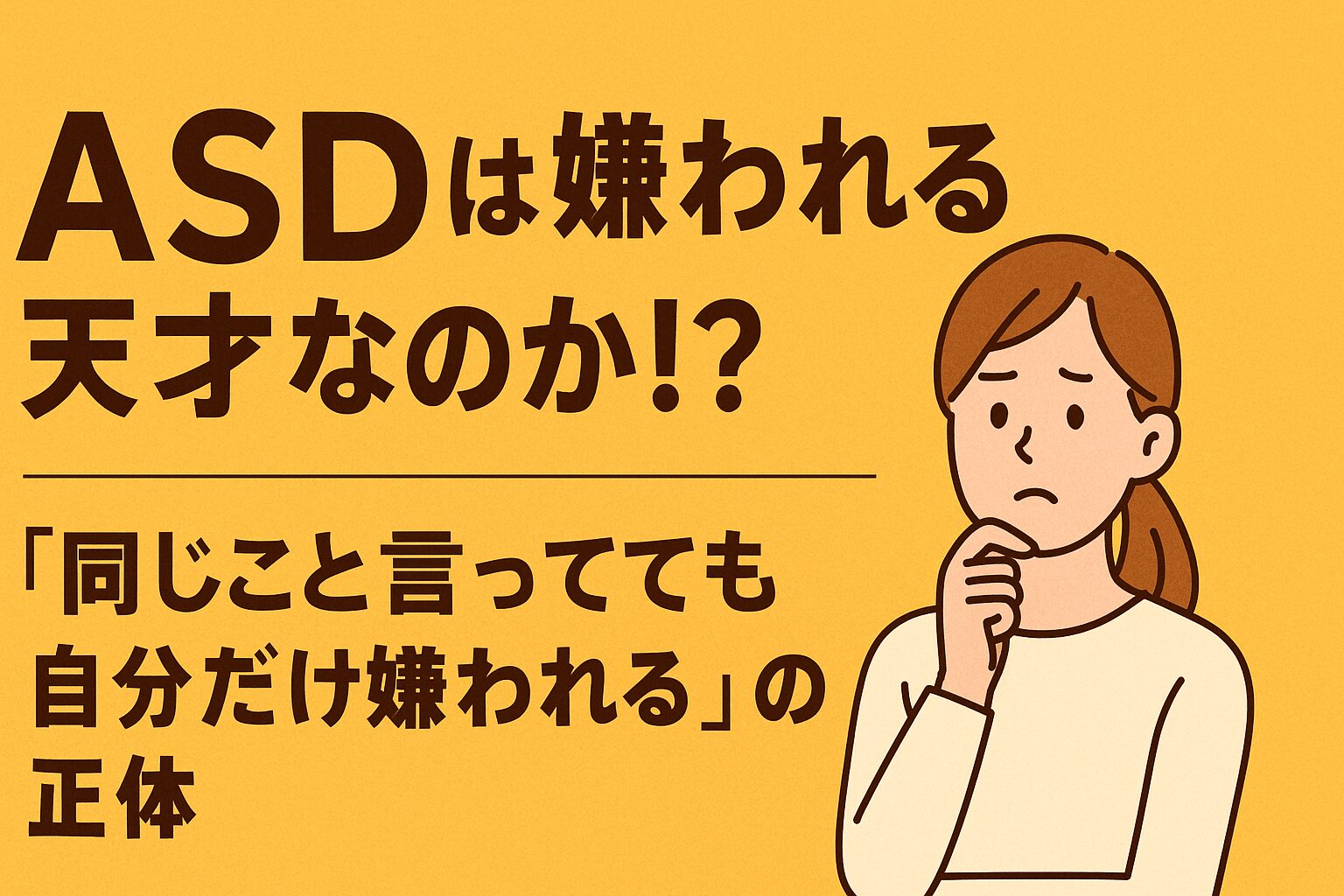

コメント